Contents Delivery Network (コンテンツ・デリバリー・ネットワーク)とは、CDN (Content Delivery Network、コンテント・デリバリー・ネットワーク)を意味する和製英語である。
コンテンツとコンテント

それぞれの意味
- Content (kənˈtent、コンテント)
- 【ITメディア用語】一般に日本でコンテンツと呼ばれている事柄に相当する
- メディア等で運ばれる中身
- [Cambridge Dictionary] Content as a singular noun is uncountable. It means the ideas that are contained in a piece of writing or a film or a speech:
- 【ITメディア用語】一般に日本でコンテンツと呼ばれている事柄に相当する
- Contents (ˈkɑn·tents、コンテンツ)
- 【ITメディア用語】英語ではあまり使われない
- 代表的な使われ方としては、以下
- 目次 (Table of Contents)
- 代表的な使われ方としては、以下
- [Cambridge Dictionary] The contents of a book is the list of chapters or articles or parts that are in the book, with the number of the page they begin on
- 【ITメディア用語】英語ではあまり使われない
ContentとContentsの使い分け(Cambridge Dictionary)
日本語の誤用例
結構あります。「応用情報技術者試験」にもあるのは痛い
- https://www.google.co.jp/search?q=%22Contents%20Delivery%20Network%22&lr=lang_ja
- 2022年3月15日の結果:4,430件
誤用の背景(サマリー)
- 日本人は、明治時代からContentsとContentを混同していた
- 1919年(大正4年)発行、現代新語辞典:Conetntsを「中身」と紹介
- 映画や映像業界では「ソフト」という用語が長らく(80年代?ごろから)使われており、「コンテンツ」という用語は比較的新しい(90年代からの)用語である。
- 使用例:CDソフト、DVDソフト
- 「コンテンツ」がIT分野で使われ始めたのはTOC(Table of Contents、目次)関連であり、これは正しい意味で使われ続けている。
- VTOC (Volume Table Of Contents):磁気ディスク関連、60年代からの用語
- TOC (Table Of Contents):CD関連、80年代からの用語
- 80年代には、CD-ROM等の目次をContentsと表記した例がある。英語に疎い一般人がこれ見て、Contentsが「CD-ROMの中身である各種ソフトウェア」を意味すると誤解した可能性が高い。また、この頃、「コンテンツ」という言葉がゲーム開発の場面で日本においても使われいたという証言もある。
- 1989年発行ディスクステーション3号の付録CD-ROM
- そして、IT分野での映画や音楽活用が騒がれた(いわゆるマルチメディア)90年代初頭に、Contentの誤用としての「コンテンツ」がIT・メディア関連の人間から一般に広がり、97年ごろに国内において定着した。
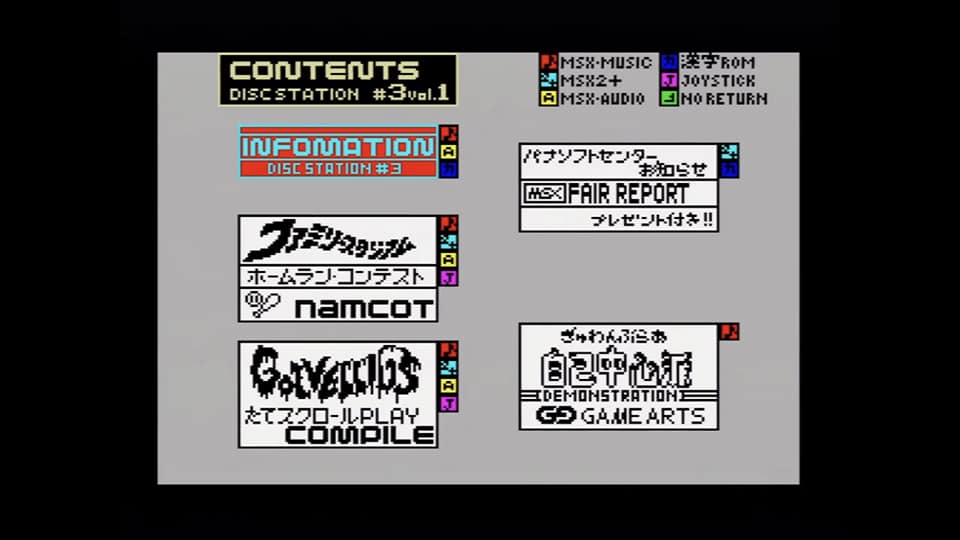
初期の「コンテンツ」使用(誤用)例
- 1919年
- 現代新語辞典
- コンテンツ(Contents)の意味として「目次、内容」をあげている
- https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/933344/46
- 現代新語辞典
- 1992年
- 日経産業新聞4月24日、アップルコンピュータ 武内重親氏
- 90年代は4つのCがキーワードになる。コンピューター、コミュニケーション、コンテンツ、コンシューマーの4Cだ
- 日経産業新聞4月24日、アップルコンピュータ 武内重親氏
- 1994年
- インターネットマガジン10月号
- 1995年
- インターネットマガジン2月号
- 1996年
- 「マルチメディアコンテンツ振興協会」
- 財団法人マルチメディアソフト振興協会から改組
- インターネット白書1996
- https://iwparchives.jp/files/pdf/iwp1996/iwp1996-ch01-01-p022.pdf
- 「Webコンテンツ」という記述がある
- 「マルチメディアコンテンツ振興協会」
日本経済新聞における登場回数
- 1992年
- 1回
- 1993年
- 5回
- 1994年
- 69回
- 調査元
参考
マルチメディア白書
- 1993年から2000年まで発行
- 1995年まで、マルチメディアソフト振興協会
- 1996年以降、マルチメディアコンテンツ振興協会
- 2001年からはデジタルコンテンツ白書となる
要調査:白書内で何時から「コンテンツ」という言葉が使われ始めたのか?
TImeMap(時間軸に着目した新方式の検索エンジン)
Wikipediaでの記述
- https://en.wikipedia.org/wiki/Content
- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84
Googleでの期間指定検索
Googleは、文書が作成された日を正確にはとらえられず、使えない。
- 1993年
- 1994年
- 1995
- 1996
ToDo
- 80年代の月刊ASCIIの調査
- ゲーム開発関連で「コンテンツ」という言葉が使われいていた可能性が高い